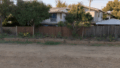ここ数年、相続登記の義務化がニュースでもよく取り上げられています。 「登記しないと罰則」と言われていますが、実際にはほとんど機能していないと感じるのが現状です。
身近にある“課税対象外”の土地たち
私の親族には、課税対象外の土地、いわゆる「放置地」がいくつもあります。 具体的には、山形県米沢に5筆、栃木県那須町に4筆、千葉県東金に4筆。 これらはいずれも固定資産税がかからない土地で、利用価値もなく、買い手もつかない場所です。
固定資産税が発生する土地については、相続登記を済ませ、きちんと対処してきました。 しかし、今後も誰も使わず、何の影響も出ないような土地については、事実上「放置」するしかありません。
相続登記義務化の“限界”
2024年から相続登記が義務化されましたが、「登記しなければ罰則がある」といっても、実際に罰金が科されるケースはごくわずか。 登記したところで売れず、活用の見込みもない土地を、誰もわざわざ費用をかけて登記しようとはしません。
このような土地が全国に数百万筆あるといわれており、これは個人の問題ではなく、もはや社会全体の構造的な課題です。
国の「引き取り制度」なくして解決はない
この問題の根本的な解決には、国や自治体が「一定条件で土地を無償で引き取る仕組み」をつくるしかないと私は思っています。 しかし、元市役所税務課に勤務していた実弟の話では、 「利用価値のない土地を引き取っても、草刈りや管理で税金がかかるから、自治体としては受けたくない」 というのが本音とのこと。
確かに、維持管理には費用がかかります。 しかし、このままでは、全国に放置地が積み重なる一方です。 結果的に、行政コストも増え、公共事業にも悪影響を与える可能性があります。
「今は関係ない土地」が、いずれ重荷になる
今は放置していても、いずれ相続が進むたびに、登記人が増え、権利関係が複雑化します。 こうなると、売却どころか処分も困難に。 「誰も得をしない土地」が、次世代の負担となるのです。
現行の制度では、自治体が土地を引き取る際に所有者側が管理費を負担する必要があります。 しかし、それでは根本的な解決にはなりません。 本当に不要な土地は、登記・税金・管理負担をすべて放棄できる仕組みが必要です。
まとめ|“義務化”だけでは解決しない
相続登記の義務化は、一歩前進ではあります。 しかし、「使い道がない土地」を前に、罰則だけで登記を促すのは限界があります。 国が本格的に「土地の引き取り制度」を整えなければ、この問題は今後も拡大し続けるでしょう。
今は静かに放置されている土地も、将来的には大きな社会問題になります。 個人任せではなく、国全体での抜本的な対策が必要です。